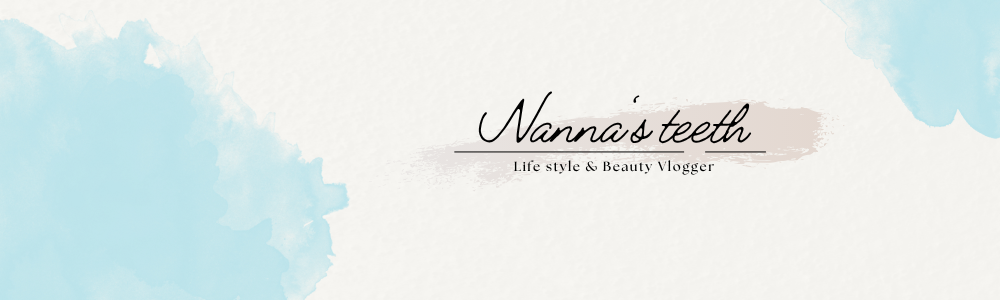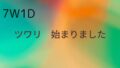胎児ドックとは?検査内容と受けるメリット・デメリット
胎児ドックとは
胎児ドックとは、妊娠初期〜中期に行われる超音波検査や血液検査を組み合わせて、赤ちゃんの染色体異常や先天的な病気の可能性を調べる検査です。
特に妊娠11週〜13週ごろに行う「初期胎児ドック」では、エコーによる首の後ろのむくみ(NT:nuchal translucency)の測定や、母体血清マーカー(妊婦の血液成分の測定)などを通じて、ダウン症候群などの確率を算出します。
一般的には以下のような内容が含まれます:
- 超音波検査:胎児の首のむくみ(NT)、心臓や骨の発達の確認
- 母体血清マーカー検査:妊婦の血液から、染色体異常リスクを推定
- 結果のリスク評価:統計学的に「可能性が高い・低い」と示される
※確定診断ではなく、あくまで「確率」を知る検査です。
私が胎児ドックを受けた体験
私は妊娠11週のときに胎児ドックを受けました。通っていた産婦人科でそのまま検査を受けられたことが大きな理由です。
賛否両論ある検査だとは思いますが、「知ることでできることがある」と考え、夫婦で話し合ったうえで受けることを決めました。
結果は「染色体異常の可能性は3000分の1程度」で、99.9%問題はないと説明を受けました。その言葉を聞いてとても安心したのを覚えています。
胎児ドックを受けるメリット
早い段階でリスクを知ることができる
妊娠初期に赤ちゃんの健康リスクを把握できるため、出産や子育てへの準備を考える時間が得られます。
必要に応じて追加検査につなげられる
もしリスクが高めに出た場合、羊水検査やNIPT(新型出生前診断)などの確定検査を検討するきっかけになります。
精密な超音波で赤ちゃんを詳しく見てもらえる
一般的な妊婦健診よりも丁寧に胎児をチェックしてもらえることが多く、赤ちゃんの姿をより鮮明に見られるのも安心につながります。
胎児ドックを受けるデメリット
確率的な結果であり、確定診断ではない
「リスクが高い」と出ても実際には問題がなかったり、「低い」と出ても絶対に安心できるわけではありません。
不安を強めてしまう可能性がある
結果の数字をどう受け止めるかは人それぞれです。リスクが少しでも高いと感じて不安が増してしまう方もいます。
費用が自己負担になることが多い
胎児ドックは保険適用外の自由診療で、費用は1〜5万円ほどかかることが一般的です。
胎児ドックに関する社会的な賛否
胎児ドックは「生まれる前に命の選別につながるのではないか」といった倫理的な議論があり、積極的に推奨すべきかどうかは社会的にも意見が分かれています。
一方で、「知ったうえでどうするかは親が決められる」「準備のために必要」と考える人も少なくありません。
大切なのは、情報を正しく理解し、自分とパートナーで納得のいく選択をすることです。
まとめ
胎児ドックは赤ちゃんの健康リスクを知るためのスクリーニング検査であり、確定診断ではありません。
- メリット:早期にリスクを知れる、追加検査の検討、安心材料になる
- デメリット:確率的な結果にすぎない、不安を抱える可能性、費用負担
私は受けてよかったと思っていますが、あくまで「夫婦にとって納得できる選択」だったからです。
これから受けるか迷っている方も、医師とよく相談し、ご自身の考えに合った判断をされることをおすすめします。
📍関連記事・あわせて読みたい
✾美容施術体験談✾ ◯わたしの日常や購入品などなど◯
▶歯科矯正治療中!◀ ▷妊娠→子育ての色々◁
X(旧Twitter)でもリアルタイムで発信しています!
よければフォローお願いします〇こちらから○
楽天ROOMもフォロー大歓迎です✾